ONODA ― 2021/10/24



イタリア映画はいかが? ― 2019/08/04
イタリアネタで今回も引っ張ってみました。
イタリアを舞台にした映画には魅力的なものがいくつもあります。
知名度が一番高いのは「ローマの休日」ではないでしょうか。ご存知、オードリー・ヘプバーンがヨーロッパ某国のアン王女役をやった1953年製作のアメリカ映画。
著作権期間50年が切れているためなのか、今やYou tubeでも観ることができます。
スペイン広場の階段でジェラートを食べる場面は有名ですが、観光客が真似るためその後、この階段では飲食禁止になっているそうです。

今や観光客でラッシュ時の駅なみの混雑

ローマの街に抜け出したアン王女と偶然知り合った新聞記者ジョーの一日のデートを物語にした作品ですが、終盤のアン王女の記者会見のシーンがおもしろいと思います。
「訪問した国々で一番印象に残った所は?」と聞かれ、ローマと言いたいところだが…と戸惑うシーンや、王女と新聞記者の立場となったジョーが公的な内容に置き換えて私的会話にしているシーンとか。
ジョーの友人のカメラマンも脇役でいい味出しています。
この映画でローマ市内の名だたる観光地が世界的に広く知られることになったとのこと。
次に紹介するのはヘプバーン主演の映画「旅情」、同じヘプバーンでもこちらはキャサリン・ヘプバーン。イギリス・アメリカの合作映画です。

アラフォの独身キャリアガールのアメリカ人ジェーンが長期休暇を取ってヨーロッパ旅行で訪れたベネチア。そこで出会ったイタリア人男性レナードと恋に落ちる、というストーリーです。
1955年製作でこれも古い映画です。ストーリー展開はちょっと退屈かな。派手でおもしろい展開があるわけではないですが、ノスタルジックな雰囲気があります。
ベネチアの風景と音楽がいい。
レナードがジェーンをくどくシーン。
「ステーキがなければパスタ(スパゲッティかラザニアと言っていたかも?)でもそこにあるものを我慢して食べたほうがいい」
という意味のことを言っていた。食に例えるのか…
次の映画はイタリア人監督による純イタリア映画「イルポスティーノ」、1994年製作。
祖国チリから亡命してきた詩人パブロ・ネルーダがイタリアのとある小島に住むことになります。郵便配達人のマリオは郵便物をパブロの家に届けるようになり、二人の間に友情が芽生え、詩や文学、芸術を教わるようになるというストーリー。
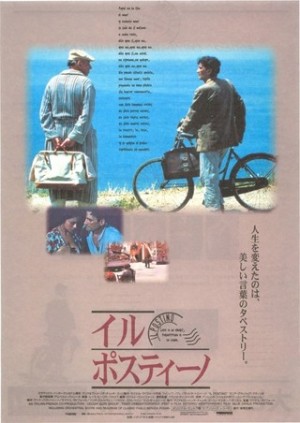
マリオがパブロに隠喩を教わるシーンがあります。
マリオ「隠喩?」
パブロ「何か話すとき、他のものにたとえることだ」
マ「例えば?」
パ「空が泣く。君はどう思う?」
そして、マリオは一目ぼれした島の娘ベアトリーチェに隠喩を使った詩でラブレターを書きます。
あの男のどこがよかったの?とおばに聞かれたベアトリーチェは「隠喩」と答える。
「言葉」と「音」がアクセントになっている、セリフのやり取りがおもしろい大人の映画です。
映画に出てくる居酒屋兼食堂はナポリ沖のプロチダ島というところがロケ地として使われました。今でもレストランとして営業しています。

中にこんな展示も

次の映画もイタリア人監督のイタリア映画。これは笑って泣けて感動できる映画です。音楽も場面、場面を盛り上げいていい感じ。
「ニューシネマパラダイス」、1988年公開の映画。

シチリア島が舞台です。故郷を出て30年、ローマで映画監督として成功を収めたサルバトーレ(愛称トト)はアルフレードが死んだことを知らされシチリア島に帰ってくる。
この場面で始まり、さかのぼって第二次大戦直後のトトの幼児期から物語は始まります。
アルフレードは村に唯一ある映画館の映写技師で、幼いトトはその映画館に遊びに行くうちにアルフレードと友人関係になり、映画にも魅了されていきます。
村では映画が唯一の娯楽で、物語はこの「ニューシネマパラダイス座(Nuovo Cinema Paradiso)」と言う映画館を中心に二人のやり取りやトトの恋愛などを交えながら展開していきます。
実はこの映画、劇場公開版より40分ほど長い完全版があります。完全版は劇場版の後日談が続いていて、劇場版でわからなかった部分が明らかになります。
(ネットのWikipediaを先に読むとネタばれしてしまうので読まない方がいい)
印象深いシーンにアルフレードが青年になったトトにおとぎ話をする場面があります。
こんな内容でした。
昔、王様がパーティーを開き、国中の美女が集まった。
警備に立った兵士がその中から王女を見てその美しさに一目ぼれする。
兵士と王女ではかなわぬ恋、どうしようもない。それでもあきらめきれず兵士は
「王女様なしでは生きていけぬ」と告白をする。
彼の思いに心を打たれた王女は言った。
「もし100日の間、私のバルコニーの下で昼も夜もずっと待っていてくれたらあなたのものになりましょう」と。
それを聞き、兵士はバルコニーの下に行った。
2日、10日、20日が経った。雨が降っても風が吹いても兵士はバルコニーの下から動かない。
王女は毎晩窓からその姿を確認した。こうして90日が過ぎ、兵士は痩せこけ涙も抑える力もなくなっていた。
そして99日目の夜…兵士は立ち上がって去って行った。
この話を聞いたトトは「なぜ最後の日に?」と問いかける。アルフレードは「分かったら教えてくれ」というだけであった。自分で考えよ、と言いたかったのかな。
ちなみにアルフレード役の俳優は先に紹介した「イルポスティーノ」のパブロ・ネルーダ役もやっています。
監督はジュゼッペ・トルナトーレというイタリア人です。この人、シチリア島出身でその後、2000年に同じくシチリア島を舞台にした「マレーナ」という映画を撮っています。

これも舞台は第二次大戦下のシチリア島。少年レナートは年上のマレーナに夢中であった。マレーナはその美貌で町中の男たちの羨望の的だったが、夫が戦場で亡くなり、マレーナは未亡人になってしまう。
思春期の少年の葛藤を、また同時に少年の目から見たマレーナの変化していく運命を描いた作品です。マレーナ役のモニカ・ベルッチはこの映画で一躍ブレーク、確かに美人です。
1997年製作のイタリア映画「ライフイズビューティフル」は監督・脚本・主演も兼ねたロベルト・ベニーニの作品で、アカデミー主演男優賞も受賞しました。
第二次大戦下のユダヤ系イタリア人家族の強制収容所での生活ややり取りをコメディ仕立てにしています。これも感動できます。
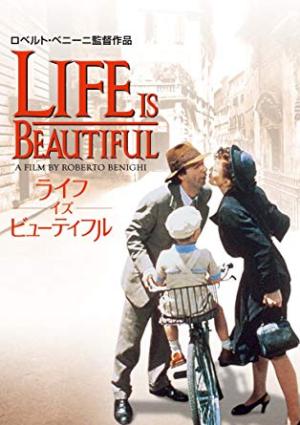
私のイチ押しは「ニューシネマパラダイス」ですね。
外出もためらう猛暑の今夏、クーラーの効いた部屋でゆっくり映画を観るのもいいものですよ。
ばってんT村でした。
炎のランナー ― 2016/08/28

盆休みと重なったこともあって私も連日、テレビで見ていました。競技のダイジェスト番組や特集番組がいくつも放映され、その中でBGMとして時々「炎のランナー」という映画のテーマ曲が使われていました。アカデミー賞も取った映画です。
そういえば、前回のロンドンオリンピックの開会式にも使用されました。
この音楽を聞いて映画を久しぶりに観たくなり、ネットで探して観てみました。公開時、映画館で1度見たきりでストーリーはほとんど忘れていましたが…・
1924年のパリオリンピックに短・中距離ランナーとして出場するイギリス人青年たちを描いたもので、脚色は多いですが登場人物は実在です。
印象深く記憶に残っていたのは、主人公の一人は敬虔なキリスト教徒なのですがオリンピックで100mレースの予選が日曜日になったことに対し、安息日である日曜日のレースを拒否したシーン、オリンピックに来た意味がなかね~、という場面です。
神に仕えるか国家に従うかという選択に迫られ…という風にストーリーが進みます。人種や宗教、国家が絡み合い、普通のスポ根ものとは少し趣は違います。
この映画ではもうひとつ思い出があります。当時、英会話を習っていてフリートークの話題に前日に見たこの映画を出そうとしたのですが英語の原題を知らなかったので戸惑ってしまいました。
あらすじを片言の英語で先に話すと、先生が「ああ、原題はChariots of Fireだね」という答え。
「Chariotとは何?」と聞くと英語で説明してくれました。
古代ギリシャ・ローマ時代の馬に引かせた二輪の戦車や競争馬車のことだったのです。映画で例を出すとすればあの「ベンハー」に競争シーンで出てきましたね。
まぁ、普通の英会話では一生でほとんど出会わないような単語なのですが、なぜかこのように印象に残ると覚えてしまうものです。
日本のアニメで日本語を覚えた外国人が、どこでそんな日本語を知ったの?というような単語を使えるのも納得がいきます。「奈落の底」なんて単語を知っているんですよ。
ばってんT村でした。
旅情 ― 2015/01/18

素敵な邦題タイトルに引かれて映画を見に行かれる方も多いでしょう。邦題はストーリーを想像させたり、観たいと思わせるようにうまく表現がされていると感じます。
で、原題はどんなんかな~と見てみると英語の原題のなんと素っ気無いこと。
昨年、大ヒットした「アナと雪の女王」の原題は「Frozen」。凍ってるってだけ言われてもねー。
おなじディズニー映画で「カールじいさんの空飛ぶ家」というのがあり、原題は「Up」、たったアルファベット2文字ですよ。
2年ほど前の同じディズニー映画で「メリダとおそろしの森」というアニメがありました。原題は「Brave」、勇気という意味ですが、確かにストーリーは勇気がポイントにはなっていました。
どうも、アメリカではタイトルで観客を呼ぼうという意図はないようですね。
時代は遡りますが、「愛と青春の旅立ち」というのがありました(今見るとちょっとクサイ邦題ですけど)。
原題は「An officer and a gentleman」。直訳すると「士官と紳士」。まあ、映画は士官養成学校生の恋と友情を描いたもので原題と合っていないわけではないですが。
さらに遡って「Melody」は邦題では「小さな恋のメロディ」(年配の方だとこの映画ご存知かと)
このように日本では原題とまったく違う邦題が付けられたり、一言付け足したりする事が多く、日本語の表現力の豊かさが感じられます。
もちろん原題、邦題ともいいなと思わせる映画もあります。私の中では、原題「Summertime」、邦題「旅情」でしょうか。(私が生まれる前の1950年代の映画なので、ビデオでしか見ていませんが)
ストーリーはアメリカ人女性が長期休暇で訪れたヴェニスでイタリア人と恋に落ちるという、時代は変わっても不変のラブストーリー物です(ヒロインは日本ではオードリーほどの知名度はないですが、大女優のキャサリン・ヘプバーン)
ちなみに映画に出てきた真紅のベネチアングラスはサマータイム(summertime)という呼び名で販売されています。
ちょっと趣味に走ってしまいましたが、原題と邦題を対比しながら映画を見るもの楽しいものですよ。
はってんT村でした。
★オリーブホームページはこちらからどうぞ!
最近のコメント