日本文化を垣間見る ― 2024/08/17










イタリアはおいしい ― 2024/05/27






ChatGPT ― 2023/02/24


落日の宴 ― 2023/01/15

タイ文字を読もう ― 2022/11/06
コロナ禍前の2019年、訪日外国人観光客数の国別順位でタイは韓国、中華圏(中国、台湾、香港)に次ぐ第5位でした。
たしかに京都でもタイ人観光客はよく見かけました。
日本人の旅行者にもタイは常時4~6位で人気の海外旅行先となっています。
外国へ行ったとき、言葉をちょっとでも話せると現地の人とふれあうことができます。さらに文字が読めるともっと楽しみが広がります。
数年前ブログで簡単なタイ語の紹介をしましたが、今回は文字の紹介をしたいと思います。
読めて、どこで使えるかって? ずばりローカル食堂です、日本と同じで地元の人が行く店は安くておいしい。タイ語のメニューしかないところも多いのでそこで役に立ちます。
(日本のラーメン屋に日本語メニューしかないのと同じです)
また、街中やホテル、空港などで目に入った文字を読んでみるというのも一興です。読めると模様にしか見えなかった文字が意味をなしてきます。
たとえば、通りでタクシーを拾おうとして探しているとフロントガラス越しに
ว่าง
と電光表示しているタクシーを見かけます。ワーン(グ)と読みますが「空いている」という意味で、つまり空車を示しています。
以前、ハングル文字の紹介をしましたが、ハングル文字よりはハードルは高いです。
ハングル文字が子音14文字、母音10文字、声調記号なしに対し、タイ文字は子音42文字、母音9文字(二重母音もあるので音はもっと多い)、声調記号4種類の組み合わせです。
また、タイ文字は子音の上下左右4方向、自由奔放に母音がくっつきます。
でも日本語はひらがな46文字、カタカナ46文字、漢字300~400(N3合格レベル)ですから文字としてはもっと難解ではないでしょうか?
日本語を勉強する外国人のたいへんさがよくわかります。
タイ語の母音は日本語「あ、い、う、え、お」とほぼ同じ発音の短母音と、「aa、ii、uu、ee、oo」と伸ばして発音する長母音や2つを組み合わせる二重母音などがあります。
例えば
า は長母音でaa 、 ไ は二重母音でai と発音
次によく出てくる子音をいくつか紹介すると
ม は m 、 ป p 、บ b、 ท th(hが付くと息を吐き出す有気音を示す)に相当
ม 、ป、บ はよく似ていますが、〇の数や棒の長さが違います。このような紛らわしい文字もいくつかあります。
でも、日本語でも「わ」と「ね」、「ソ」と「ン」のように類似形がいくつもあるのと同じですね。
さて、これら母音と子音を組み合わせると、
例えば ม m と า aa
มา で maa マー、これは「来る」の意味です。子音の右側に母音がついています。
同じつづりでも ม้า と上に声調記号がつくと「馬」の意味になります。
これは高い音からさらに高く発音します。
ป p と ไ ai で
ไป pai パイ、「行く」の意味です。 これは左側に母音ไ ai がくっついています。
ไทย 国名である「タイ」はこう書きます。
ไท これだけでthaiと読めるのですが、後ろに子音の ย yが付きます。
บาท タイの通貨単位であるバーツはこう書きます。
分解するとบ b と า aa で บา baa
この後ろに ท th が付いてbaath
日本語でバーツと言ったり書いたりしますが、タイ語の発音では最後のツはほとんど聞こえません。
ちなみに、タイの代表的な料理、エビのスープ料理であるトムヤムクンはこう書きます。
ต้มยำกุ้ง
これは3つの単語の合体です。
ต้ม トム 煮る、ゆでる
ยำ ヤム 和える、混ぜ合わせる
กุ้ง クン エビ
上で紹介していない文字も入っていますが、少しずつ憶えていけば短い単語なら読めるようになります。
メニューであれば、飲み物か料理名しか書いていないので読めない文字が混じっていても、まぁ推測がつきます。文字を読むいい勉強になるんです。
これがメニューの一例ですが、左側の一番上はソムタムと書いてあります。青いパパイヤを使ったサラダのことでこれもタイのポピュラーな料理です。

ドラマ、映画、ポップスなどで韓国ブームが続いていますが、ファンはやはり韓国語を勉強する動機になるそうで、オリーブに見学に来ていた中国人女性も韓国語を話せてハングルも読める、と言っていました。
このように好きだからというきっかけで外国語を勉強するのが一番いいのかもしれませんね。
ばってんT村でした。
英仏を巡って ― 2022/09/25

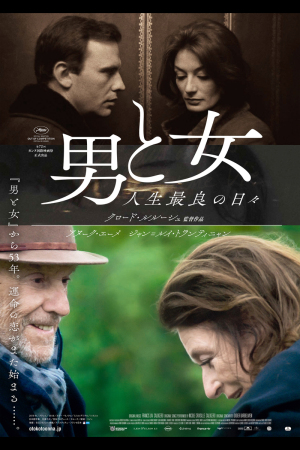

アメリカ図書館 ― 2022/09/11


沖縄と滋賀 ― 2022/08/14

あこがれの小堀 ― 2022/06/18

勘違いのことば達 ― 2022/06/05
前回ブログの冒頭、本屋さんの店員が「手帳」と「店長」を聞き間違えた話をしましたが、外に出ると図らずも面白い目に合うことがあります。
私はよい意味で、犬も歩けば棒に当たる、と勝手に解釈しています。
初めて読む人もいらっしゃると思いますので、以前ブログで書いた同じ話もあって恐縮ですが改めて私の経験を。
言葉に関することなので、チョット参考になるかもです。
●コピーをください
若い頃は、仕事の出張で頻繁に韓国に行っていました。
単独で電車やバス、タクシーで移動したり、街中の食堂でご飯を食べたりする機会も多かったので、最低限必要な韓国語を事前に勉強したり、現地で憶えたりしていました。
1980~90年代、日本に追いつけ、追い越せで韓国では日本語の勉強熱が高かった時代です。
それもあってか、仕事先では一定の職級以上の人は日本語が問題なく話せたので業務上の会話は日本語でした。
ある顧客の会社で打ち合わせをやっていた時のことです。使っていた資料のコピーが必要になり、近くにいた女性社員(日本語は話せない)に自分の手元の資料を指さして「コピーチュセヨ」とお願いしました。
韓国語でチュセヨ、とは「ください」の意味です。
女性は「ネ~(はいの意味)」と言ってそのまま部屋から出ていきました。
しばらくすると、その女性は紙コップに入ったコーヒーを持ってきて、私の前に置いたのです。
コピーを頼んで、なぜコーヒーが出てきたのか私はわけがわかりませんでした。
これを見て、打ち合わせに同席していた人が笑いながら「T村さん、coffeeは韓国語でコピと言います」
「では複写する意味のコピーはどう言うんですか?」と聞くと「それはカピと発音します」
日本語と同様、韓国語では外来語をそのまま使うことが多いのですが、韓国語特有の発音になります。
例えばスポーツのゴルフは韓国語ではコルプと発音します。これなど、さらにわかりにくいと思いますね。
●グラスをください
これはフランスに出張した時のことです。
フランス語が堪能な日本人の商社員を含め数人でレストランに入りました。
飲み物を含めた注文後、ガラスコップが一つ足りないことに気づき、ウェイターに「One glass please」と英語で言いました。
しばらくしてウェイターが持ってきてテーブルに置いたのは、アイスペールに入った氷だったのです。氷をつかむトングも付いていました。
氷は注文していないけど、と不思議に思っていると商社員の方が笑いながら
「あ~、たぶん英語のglassを誤解したのだと思います。フランス語でグラスと言うとアイスクリームや氷を意味します」
あとで調べてみると、言われるようにフランス語にglaceという単語がありました。
●ホテルの名前はアルベルゴ
これははじめてイタリアに出張した時のことです。
現地の商社員の方にミラノの空港でピックアップしてもらい、郊外の小さな町のホテルにチェックインしました。
翌日、顧客先で仕事の終了後、相手をしてくれた人が「車でホテルまで送っていきますよ。ホテルはどこですか?」と聞かれました。
会話は英語です。
ホテルの表の看板に「ALBERGO」と書いてあったのを覚えていたので「アルベルゴに泊まっています」と答えました。
これ、しっかり記憶していたんですが

すると「OK、それでホテルの名前は?」と再度聞いてきます。
私が困惑していると、彼がわかった、というような表情で「ホテルをイタリア語でアルベルゴと言うのですよ。」
日本語で言えば、単に「旅館」とだけ書いた看板がかかった宿みたいなものなのでしょう。
私が泊まったこの「アルベルゴ」は食堂もあって、夕飯時になると主人が部屋のドアをノックして知らせてくれるような小さな宿でした。
ドアを開けると、「マンジャーレ」(イタリア語で「食べる」の意味)と言って私に向かってジェスチャーで食べるしぐさで準備ができたことを教えてくれるのでした。
●ちょっと待って
アメリカの顧客先工場で日本人の現地駐在員と一緒に行った時のこと。
顧客と打ち合わせをやっている最中、要所要所でこの駐在員と二人で日本語だけで話すことがありました。
相手に返事する前に見解を合わせておく時や聞かれたくない内容の時です。
すると後から「チョットマッテ、はどういう意味ですか?」と聞かれたのです。我々の会話の中から聞き取ったみたいです。
この「チョットマッテ」、拗音と促音が入る日本語、発音的にアメリカ人にも印象に残ったのでしょう。
確かに会話でちょくちょく使うと思います「調べるからちょっと待って」とか「ちょっと待って、考えさせて」とか。
意味を教えた後は、一緒に作業などしている最中、そのような場面が来たら嬉しそうに「チョットマッテ」と日本語で言ってくるのでした。
日本に来る外国人観光客だと、「アリガトウ」の次によく聞く日本語は「イラッシャイマセ」ではないでしょうか?
これはどこで聞かれたかは忘れたのですが、「エートはどういう意味ですか?」という質問もありました。
うん、確かにしゃべっている合間に挟むな。「えっ~と、それはね・・・」、当時は説明できませんでした。
「え~」とか「あの~」はFiller(フィラー)と呼ばれる発話の合間に挟む、それ自体意味を持たない言葉です。
内容を発話前に頭の中で思い出したり、整理したり、また相手にこちらが考え中だということを認識してもらうためにも有効なものです。
多用すると聞き苦しくなるのでなるべく使うなとも言われますが、これやらないと発話の途中で沈黙ができます。
特に顔が見えない電話の時はなにかあったのか?と思われたりします。
コミュニケーション、おもしろくもあり悩ましくもあり、ですね。
ばってんT村でした。
★オリーブホームページはこちらからどうぞ!
最近のコメント